国民年金法と厚生年金保険法の条文から、
日常ほとんど使わない、次の用語の意味を調べてみました。
・管掌「かんしょう」
・裁定「さいてい」
用語の意味
管掌(かんしょう)の意味
管掌(かんしょう)
岩波国語辞典:つかさどること。自分の管轄の仕事として監督し取り扱うこと。
新明解国語辞典:自分の管轄の仕事として責任をもって取り扱うこと。

条文をみてみましょう。
国民年金法の場合
(管掌)「かんしょう」
法3条
1 国民年金事業は、政府が、管掌する。
2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、、、、又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされたに行わせることができる。
3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、が行うこととすることができる。
国民年金法3条
厚生年金保険法の場合
(管掌)「かんしょう」
法2条
厚生年金保険は、政府が、管掌する。
厚生年金保険法2条

「管掌する」のは
国民年金も政府
厚生年金保険も政府。
両方とも政府が管掌する。
裁定(さいてい)の意味
裁定(さいてい):
岩波国語辞典:物事の理非・善悪をさばいて決めること。裁断。
新明解国語辞典:相対立する当事者間に意見の不一致がある場合に、第三者が裁断を下すこと。

条文をみてみましょう。
国民年金法の場合
(裁定)「さいてい」
法16条
給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、が裁定する。国民年金法
厚生年金保険法の場合
(裁定)「さいてい」
法33条
保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、が裁定する。
厚生年金保険法

「裁定する」のは
国民年金は厚生労働大臣が裁定
厚生年金保険は実施機関が裁定。
実施機関とは(用語の定義)
実施機関は国民年金と厚生年金保険で同じではない。
国民年金法第5条 (用語の定義)
・ この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等をいう。
・ この法律において、「実施機関たる共済組合等」とは、厚生年金保険の実施機関たる、又はをいう。
厚生年金保険法第2条5
この法律における実施機関は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第1号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務
二 に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第2号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務
三 に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第3号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務
四 に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第4号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務
過去問題
管掌
厚生年金保険は、厚生年金保険法に定める実施機関がそれぞれ管掌することとされている。
平成30年 厚生年金保険法 問7
答え:× 誤り。
「厚生年金保険法に定める実施機関がそれぞれが管掌する」ではない。
「政府が管掌する」。

「管掌する」のは政府。
裁定
保険給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
平成22年 厚生年金保険法 問1
答え:〇 正しい。
保険給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基いて、実施機関が裁定する。
(平成28年法改正)
「厚生労働大臣」との文言が、「実施機関」に改められた。

「裁定する」のは
国民年金は厚生労働大臣
厚生年金保険は実施機関
老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、当該遺族厚生年金の裁定請求を行う場合には、厚生労働大臣は、当該受給権者に対し、老齢厚生年金の裁定の請求を求めることとする。
平成22年 厚生年金保険法 問7
答え:〇 正しい。

「裁定の請求を求める」のは
厚生労働大臣・・・。
余計なこと
パターン1

セーフで完勝する

大臣あるいは
その実子
選挙期間は咲いて。

政府で管掌する。
大臣あるいは
実施 機関は
裁定。
パターン2
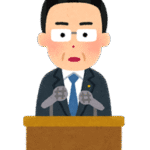
内政不干渉
(ないせいふかんしょう)
=ない政府・管掌

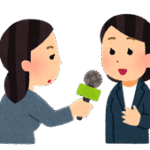
「大臣、実施最低?」
(大臣は、〇〇実施していないのでは?)
以上 ご覧いただき、ありがとうございました。



コメント